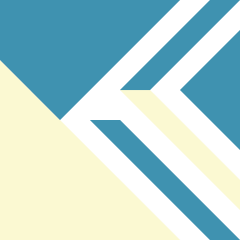「スーパーラット」シリーズや、帰還困難区域内で封鎖が解かれるまで観に行くことが出来ない国際グループ展「Don’t Follow the wind」、広島での「ヒロシマの空をピカっとさせる」など、現代社会に全力で介入したメッセージ性の強い作品を次々と発表し、今や国内にとどまらず、世界のアートシーンからその活動が注目の的となっている「Chim↑Pom(チンポム)」。
2005年、卯城竜太、林靖高、エリイ、岡田将孝、稲岡求、水野俊紀の6人が結成した「Chim↑Pom」と「新宿」との関わり、これまでの作品作りと未来への思いを、メンバーの卯城氏に聞いた。

新宿・歌舞伎町を舞台にした作品も多く発表されていらっしゃいますが、街との関わりのきっかけをお聞かせください。
結成初日に集合したのが、まさしく歌舞伎町の街でした。メンバーみんな、絵を描いたり彫刻を作ったりというスキルを持たずにぶらぶらしていたし、何をやったらいいのかもわからなくて、当時安かったビデオカメラを買って何か撮ろうと、交通の便の良い新宿に集まったんです。バッティングセンターでボールに当たったり、街なかに貼ってあるポスターにジャムを塗って舐めたりしているところを撮ってみたり(笑) それが初めての作品作りでした。当然全部お蔵入りです(笑)
 Courtesy of the artist, ANOMALY and MUJIN-TO Production
Courtesy of the artist, ANOMALY and MUJIN-TO Production結成翌年の2006年に発表されたプロジェクト「スーパーラット」は新宿ではなく、渋谷が舞台となった作品でしたね。
(「スーパーラット」:都市に増殖するネズミを実際に網で捕獲、その剥製を黄色くペイントし、捕獲映像とともに展示した作品)
最初の作品作りの後、活動スタイルというか、活動の拠点が「渋谷」になったんですね。「スーパーラット」というのは、殺鼠剤などの毒とか罠に耐性をつけて対抗、繁殖していくネズミの愛称で、駆除業者によって名付けられたんです。
2008年には「BLACK OF DEATH」という作品(捕まった仲間を助けようと集まるカラスの習性を利用し、カラスの剥製と音声を使ったゲリラアクション)も発表したんですが、ネズミやカラスの数でいうと、本当は新宿の方が渋谷より多くて制作しやすかったんです。渋谷には「109」とか駅前にモニュメントなどがあって、それがどこなのか、どういう文化なのか、見ればみんながパッと思い浮かべることができたんですね。歌舞伎町辺りには意外にそういったものがなくて結構難しかった。けどいまはそのモニュメントに頼らず、小さい店が密集しているのが歌舞伎町の魅力だと思っています。
 Courtesy of the artist, ANOMALY and MUJIN-TO Production
Courtesy of the artist, ANOMALY and MUJIN-TO Production2011年に起きた東日本大震災と福島第一原発での事故を受けて、ライフスタイルを変えなきゃいけないとか、汚染についてとか、どう自分をサバイブさせていけば良いかといったことを考える中で、もう一回「スーパーラット」を作り直そうと思いました。そのとき、制作の舞台を渋谷から歌舞伎町に移しました。
というのも、渋谷はどんどん浄化されてきれいになっていって、ネズミたちは住処を移していったんですよ。繁華街の中心で彼らと街をワイルドにシェアしている感じが面白かったのだけど、彼らがいなくなってくると面白みもなくなっていきました。
そこで新宿に戻ってみると、歌舞伎町はまだネズミとの距離感もすごく近くて、「まさにアジアっぽいな」と(笑)
カラスは早朝に多くいます。その時間に街に行くんですけど、渋谷より歌舞伎町にいるカラスの方が、人への距離感が近い感じがありました。「人」だと認識はしているけど、もうちょっと自分たちに近い生物だと思っているような、そんな風に感じられたのです。
ワイルドな「街」そのものに、人の雰囲気がフィットしているからだと僕は思うんです。そこにいる人たちもネズミ同様「野良」っぽいというか(笑) 新宿の、そうしたジェントリフィケーション(都市の居住地域を再開発などで活性化、高級化すること)されていない感じが僕らはすごく好きで、それ以来、この作品は歌舞伎町で制作しています。

「街が浄化されていく」とお話しにありましたが、「スクラップ アンド ビルド」などをテーマにした作品も発表されてきた中で、現在の、急速に街が新しく生まれ変わっていく様子については、どう見られていますか?
街に新しいものができると、まずはそこに行ってみるんです。でも年々、街、公共の場など、東京の多くの再開発地区はそこにいる人のタイプというのが偏ってきているなと感じます。「公共」っていろいろな人たちがいて、それが許容されるから公共なんだけど、そういう体裁はあっても、そこに集う人たちのタイプが限りなく1パターンのように見えるんです。
でも歌舞伎町はそうじゃないんですよ。多様性のある街などと言われているけれど、何かそんなキャッチフレーズがアナウンスされなくたって、そもそもいろんな野良な人たちが同時に存在しているような自然さがある。そのアイデンティティこそが、唯一無二な街の魅力になってるんでしょうね。
新しく出来た公共の場に行って「ここにいる人たちのタイプは何だろう」と考えてみると、おそらく彼らは、与えられたものを受け取る「消費者」なのではないかと思います。一方、歌舞伎町は、みんなが街をいわば「当事者」としてシェアしている感じがします。カラスやネズミもそうですよね(笑) 自然の生き物たちと人間の距離が近いように感じたり、アジアっぽいと感じたりするのも、彼らの「当事者」性からくるのではないかと思います。
東京のほかの街も、画一化してきていると感じられますか?
そうですね。都市はどこでも「テーマがセレクトされた公共」空間としてデザインされていますけれど、繁華街だからといって、そこに何か名前をつけたりテーマを与えてしまったりすると、その瞬間からこうしなきゃいけない、こうでなきゃいけない、これをしてはいけないという「暗黙の設定」が出来て、人の行動をその1つのパターンに落とし込んでしまう。そうすると最初からそこにいる人たちや、新たに街に来た人たちがどんどんパターンを作っていけるような自由さがなくなってしまうと思います。
歌舞伎町には性的マイノリティーや外国人もたくさんいるし、多様なマイノリティーの人たちが集まってそこをシェアしているというのが街のアイデンティティだと感じますから、そもそも東京の画一化している方向とは最初から違うし、だからこそ唯一、その自由さが失われていないように思います。

海外でも多く作品を発表されていますが、世界から見た新宿の印象はいかがでしょうか?
僕らの周りのアートシーンにいる敏感な外国人たちは、どこの街より歌舞伎町に連れてくると、「これこれ!」っていう顔しますね。ユニークだからみんなびっくりするけれど、多様性という観点からは、とてもリアリティがあって、誰もがフィットできるのではないかと思います。自分たちがそもそも知っている世界、またアイデンティティとして求めているもの、「ワォ!」っていうサプライズ、それらのバランスが最高に良くて、みんな喜んでくれるのだと感じます。
渋谷なら「街」そのものというより、具体的におもしろい「店」となることが多いけれど、新宿には、例えばロボットレストランやいろいろなタイプの店が集合したゴールデン街、すごく偏った個性的な店やアート好きを惹きつける謎なスポットなどもあって、カオスですよね。どんだけ知っても未知の領域が先に広がってそうだし。そんな「街」全体が刺激的なんだと思います。
例えば、海外で最近で面白いと感じる街はありますか?
今年の夏に僕らも初めて参加する「マンチェスター・インターナショナル・フェスティバル」が行われるマンチェスター(イギリス)はおもしろうそうだと思っています。
「マンチェスター・インターナショナル・フェスティバル」は、まだスタートして10年くらいのイベントですが、街中を使い、演劇、音楽、アートが全部混ざり合って行われるイベントです。今や各界のトップアーティストや大御所も参加しています。面白いことに、一つ約束事があって、出品する作品は全部新作でないといけない。そこで、例えばペインティングでも、ただ「作品を一つ作りました」ということには誰もならなくて、ほぼすべての作品、参加者全員が何かプロジェクトのような形になるんです。
このイベントの興味深いところは、10代、20代の若者を、運営側がまさにイベントの「当事者」として積極的にピックアップして育てる仕組みもあるところです。数人の若者がヤングキュレーターとして、何をするか決め、キュレトリアルコレクティブを作る、といった企画があるんですね。「Chim↑Pom」は今回その枠に選ばれて参加するのですが、彼らは自ら、世界中のさまざまなジャンルのアーティスト300近くをリサーチして、議論するんです。今回その結果、僕らを選んでくれました。若い彼らにチャンスを与え、実践的に育てているのが最高だなと。日本だとエラーを恐れてトライしないじゃないですか。だから若者も保守的になる。
マンチェスターでは数年前、このフェスティバル開催の数週間前に犠牲者がでるテロが起こりました。イギリスのテロのことを思いだされる方もいらっしゃると思うのですが、まさにこのイベントの直前のテロだったんですね。この時の話を聞くと、とても興味深いのが、その翌日には自然発生的に多くの人が、「みんなで街に集まろう」、「分散したらダメだ」と行動を起こしたということです。沈黙の中、1人がマンチェスター出身のロックバンド「オアシス」の有名な楽曲「Don’t look back in anger」を歌い始めた。それが次第に、周りの人々全員に伝播して大合唱になった。そして、この人々の強い思いがあったからこそ、イベントの運営側も行政と共にフェスティバル自体を中止することなく、「街なかは使う、人も集める、では警備はどうしたら良いか」とプラクティカルなところに集中して物事を進められたそうです。日本であったら、どうでしょうか。たぶん、即座に人が集まるイベントは中止、としか考えないのでは、と思います。行政のリスクマネージメントの考え方と、人々の行動の違いを感じます。マンチェスターの彼らは「文化」が強いと思っているし、こうした経験を経て、彼らの中にマンチェスターとしての確固たるアイデンティティーや、団結心みたいなのもがさらに強く育っていると思います。マンチェスターに行くと、彼らがプライドを持っている感じが伝わってきます。そして、失敗を恐れないで進む、その姿勢もいいなと思います。