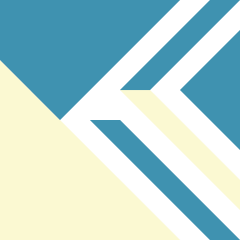その形から辛さまでさまざまな種類がある唐辛子だが、新宿に縁の深い唐辛子に「内藤とうがらし」がある。歌舞伎町のほど近くにある花園神社の境内には「江戸・東京の農業 内藤トウガラシとカボチャ」と題した銘板が立てられていて、これを読むと「新宿周辺から大久保にかけての畑は、トウガラシで真っ赤になるほど」その栽培が盛んだったことがわかる。
現在JR新宿駅に設置されている「駅のスタンプ」にも内藤とうがらしは見られる。2020年に絵柄を一新した際、「駅やその地域の歴史・特徴などを表現するもの」としてデザインされた。今回はそんな新宿の名産品「内藤とうがらし」について紹介したい。

「内藤とうがらし」の「内藤」は江戸幕府誕生の際、徳川家康から新宿を含む広大な土地を拝領した鉄砲隊の武将・内藤清成に由来する。後に江戸の中心と、西の郊外や甲州を結ぶ主要な街道が交わる物流のターミナルとなった現在の新宿一丁目から三丁目辺りに、自然発生的に宿場が形作られるのだが、これが内藤家の屋敷にちなみ「内藤宿」と呼ばれた。やがて浅草の商人らの発起によって幕府管掌の新たな宿場町「内藤新宿」が開設され、江戸に近い行楽地・繁華街として本格的ににぎわうようになる。
この頃、現在の新宿御苑に下屋敷を構えていた内藤家ではさまざまな野菜を育てていた。8代将軍徳川吉宗が野菜作りを奨励したこともあり、武家屋敷内でも畑を持ち野菜を作って自給する慣わしがあったという。中でもこの辺りで栽培するのに適していた唐辛子は「内藤とうがらし」として評判になり、やがて新宿一帯で広く作られるようになった。
戦国時代だった1500年代半ば(諸説あり)に日本に伝来した唐辛子は、当初は食用ではなく漢方として扱われていた。1652(寛永2)年に日本橋薬研堀町(現在の東日本橋)のからしや徳右衛門が漢方薬を基に七味唐辛子を作って売り出したことで、食材として全国に広まったのである。とりわけ働く男たちが多く集まっていた江戸の町には、彼らが好んだ手軽で安い蕎麦が流行し、薬味として蕎麦に合う内藤とうがらしの需要も一気に高まったのである。農作物を換金できる制度もあったため、特に内藤新宿周辺の農家たちは皆この唐辛子を生産し始めた。
内藤とうがらしは「八房系」と呼ばれる種類の唐辛子である。房のように集まって付いた赤い実が葉の上部に上向きに付くため、収穫時には畑一面が真っ赤な絨毯を敷いたように見えたのだろう。しかし唐辛子の栽培は明治に移り、都市が近代化する過程で途絶えてしまう。より刺激的な辛みを持った「鷹の爪」が出てきたことも絶滅の要因となったと言われている。
そんな内藤とうがらしが近年、新宿界隈で復活している。かつて地域ブランドであったその存在を知った市民グループが中心となり、2010(平成22)年に「内藤とうがらしプロジェクト」を発足、プロジェクトリーダーを務める成田重行さんらメンバーが、八房系の古い種を探し、固定種として育てることに成功したのである。2013(平成25)年には伝統の江戸東京野菜に認定された。
現在では新宿周辺の企業、店舗、団体、学校が内藤とうがらしを地域ブランドとして育てる活動に取り組むほか、飲食店による地産地消を目指したイベント、苗の販売などが行われている。
 成田重行さん(写真提供)「スタジオ104 at FAVETTA」
成田重行さん(写真提供)「スタジオ104 at FAVETTA」「珈琲西武」などの飲食店を手がける三信商事株式会社は、2020年10月に同プロジェクトと連携し、歌舞伎町の「Trattoria Pizzeria Bar FAVETTA」内に、「スタジオ104 at FAVETTA」を併設した。コロナ禍にあって、地元企業として新宿を盛り上げたいと考える中でプロジェクトと出会い、自社で管理するビルの屋上で内藤とうがらしを栽培するなど少しずつ取り組みを進めてきた。同レストランでは栽培した内藤とうがらしを使ったメニューも提供している。レストランに食事に来て初めて内藤とうがらしを知り、スタジオに立ち寄って商品を購入する人も増えているという。
 真っ赤な「内藤とうがらし」を散りばめた「スタジオ104 at FAVETTA」(写真提供「スタジオ104 at FAVETTA」)
真っ赤な「内藤とうがらし」を散りばめた「スタジオ104 at FAVETTA」(写真提供「スタジオ104 at FAVETTA」)新宿中央公園では2021年秋に「新宿の伝統野菜」と題した内藤とうがらしの展示を行った。種を採取し公園内で育てることで長く継続して展示するなど、同公園では今後も関連したイベントを行っていきたいと話す。


他にも、新宿の老舗映画館「新宿武蔵野館」、姉妹館「新宿シネマカリテ」では七味を全種類常設するなど内藤とうがらしを地域の名産として応援する動きが見られる。400年の時を経て復活した新宿の名物 内藤とうがらしの今後の広がり、新宿での活動にぜひ注目してもらいたい。
参考資料
『情熱の! 新宿内藤とうがらし〜新宿名物誕生物語〜』 新宿〜御苑〜四谷タウン誌「JG」 編集部(2016年、H14)